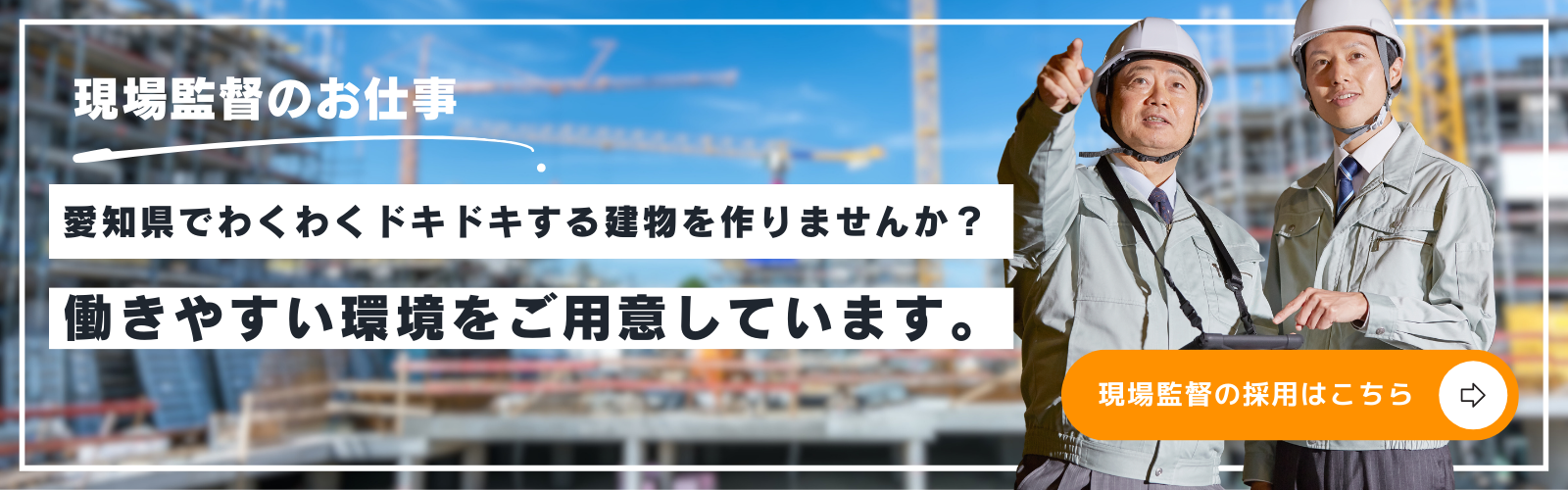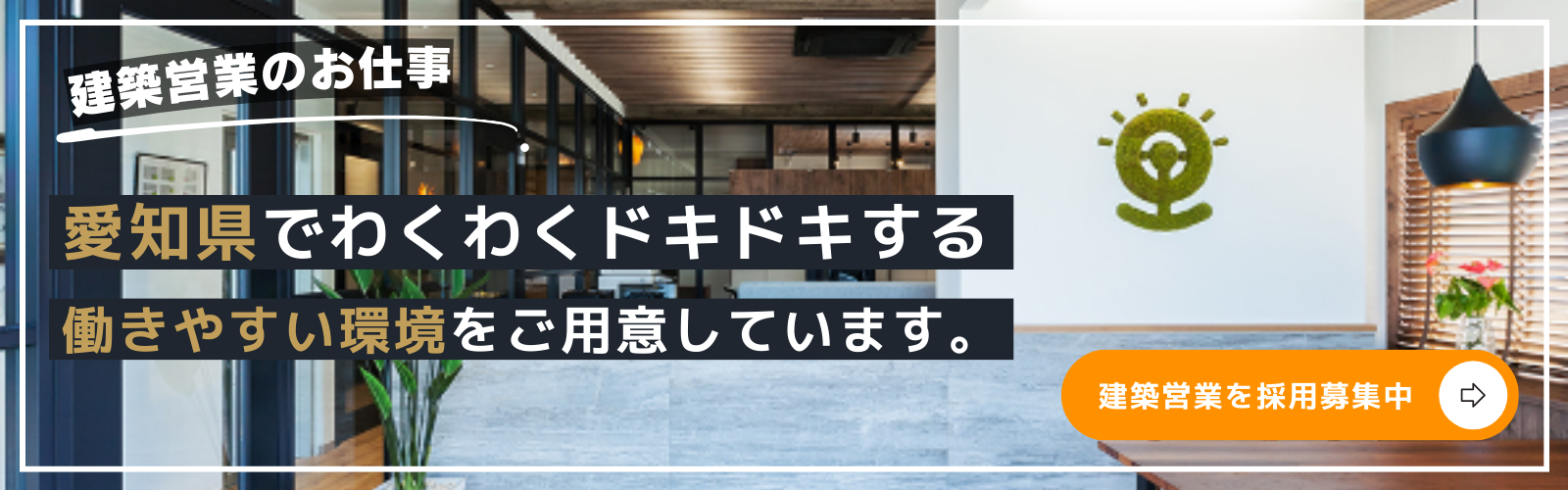この記事では次の内容をまとめています。
- 倉庫を鉄骨造にするメリットとデメリット
- 倉庫を木造にするメリットとデメリット
倉庫を鉄骨造と木造のどちらにしようか考えている方が知っておくべきことを全てまとめました。
倉庫は鉄骨造と木造どちらが多い?
全国の倉庫の7割強が鉄骨造、2割が木造と言われています。
つまり、鉄骨造の倉庫の方が圧倒的に多いことが分かります。
ただし、鉄骨造にも木造にもそれぞれメリットとデメリットがあるため、倉庫に何を求めるかによって、どちらを選ぶべきかは異なります。
倉庫を鉄骨造にするメリット6つ
この章では倉庫を鉄骨造にするメリットをご紹介します。
| 1 | 耐久性・耐震性が高い |
| 2 | 部材の品質がいい |
| 3 | 耐火性が高い |
| 4 | 遮音性が高い |
| 5 | 大空間を実現できる |
| 6 | 解体費用を安くできることも |
耐久性・耐震性が高い
鉄骨造の大きなメリットは耐久性や耐震性が高いことです。
部材が丈夫なため、建物全体の耐久性は高いです。
倉庫は多くの荷物を置くため、耐久性が高いと安心です。
また、日本は地震が多い国なので、耐震性が高いと従業員も荷物も守ることができます。

部材の品質がいい
鉄骨造の建物に使われる部材は品質が高く、安定しているという特徴があります。
これは部材が工場で生産されるためです。
また、この性質により、建物の出来が職人の腕に左右されにくいというメリットもあります。
安心して建設を依頼できるのは大きな強みです。
耐火性が高い
木造に比べて鉄骨造の方が耐火性が高いです。
ただし、鉄骨造は軽量鉄骨造と重量鉄骨造があり、厚さ6mm未満の鋼鉄を使う軽量鉄骨造の方は部材が薄いため、熱が加わると溶けたり、歪んだりしやすいです。
軽量鉄骨造でも重量鉄骨造でも、耐火被覆工事を行えば耐火性をさらに高めることができます。

遮音性が高い
鉄骨造の倉庫は木造に比べて遮音性が高いです。
外の音が聞こえにくいと、従業員は作業に集中して取り組むことができます。
また、倉庫内の音が外部に漏れないことで、騒音トラブルを防ぐこともできます。
近くに他の建物がある場合には大きなメリットになります。
大空間を実現できる
鉄骨造は耐久性が高いことから、様々な構造を実現することができます。
柱をできるだけ少なくした大空間を作ることも可能です。
そのため、倉庫なら保管エリアの天井を高くし、上に収納できるようにすることで、保管効率を上げることができます。
例えば、パレットにダンボールをいくつも載せたものを、フォークリフトで上げて天井近くに収納するといったことも可能です。
倉庫に広い空間を作りたい、大きな荷物を扱う、より多くの荷物を収納できるようにしたいという場合は鉄骨造がおすすめです。
解体費用を安くできることも
倉庫は建設時だけでなく、解体時にも費用がかかります。
このとき、建物を支えていた鋼鉄は有価材として業者に有料で引き取ってもらえることがあり、結果として解体費用が安く済むことがあります。
ただし、錆がひどいなど、鉄骨の状態によっては引き取ってもらえないこともあるので注意が必要です。

倉庫を鉄骨造にするデメリット3つ
この章では倉庫を鉄骨造にするデメリットをまとめました。
| 1 | 工期が長い |
| 2 | 断熱性が低い |
| 3 | 錆びやすい |
工期が長い
鉄骨造の倉庫の工期は木造に比べて長いです。
また、工期が長いとその分、稼働する人や時間が増えるため、建築コストも上がります。
ただし、鉄骨造は工場で梁や柱を組み立てるため、現場での作業時間が短縮されます。
木造より長くかかりますが、鉄筋コンクリート造よりは工期は短いです。
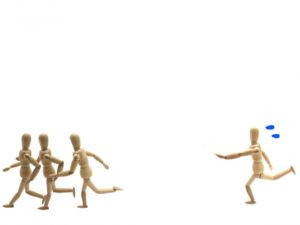
断熱性が低い
工場は断熱性が低いです。
つまり、外気に合わせて夏は暑くなりやすく、冬は寒くなりやすいということです。
特に夏は熱中症のリスクが高くなり、従業員の健康を脅かす恐れがあります。
空調設備を整えて1年を通して快適に過ごせる環境作りが不可欠です。
断熱性を高くするためには壁に断熱材を入れるなど、建設段階からできる対策もあります。

錆びやすい
鉄骨造のデメリットといえば部材が錆びやすいことです。
丈夫なのが強みの鉄骨造ですが、錆びると性能が落ちて耐久性や耐震性に影響を与えることがあります。
そこで、防錆加工を施しておくなど、錆対策をしておくことが欠かせません。

倉庫を木造にするメリット4つ
この章では倉庫を木造にするメリットをご紹介します。
| 1 | 建設コストが安い |
| 2 | 鉄骨造が建てられない土地でも建てられる |
| 3 | 外気の影響を受けにくい |
| 4 | 減価償却が短くて節税になる |
建設コストが安い
木造の大きなメリットは建設コストを抑えられることです。
これは鉄骨造で使われる部材よりも木材の方が安いからです。
また、鉄骨造の建物は全体の重量が大きいため、場合によっては基礎工事や地盤改良工事にコストが多くかかることがあります。
一方で、木造は全体的に軽いため、このようなコストがかかりにくく、安く済みます。
倉庫の建設コストを少しでも安くしたいという方には木造が合っています。

鉄骨造が建てられない土地でも建てられる
先ほども述べたように、鉄骨造は重量があるため、地盤調査の結果、建てられないと判断されることがあります。
一方で、木造は鉄骨造よりも軽いため、鉄骨造では建設できない土地でも建てられることがあります。
このように、建設できる土地の幅が広いのが魅力です。

外気の影響を受けにくい
木造の倉庫は断熱性が高く、外気の影響を受けにくいです。
そのため、夏には室内の温度が上がりすぎるのを防ぐことができ、また、冬には建物内の暖かい空気が外に逃げるのを防ぐことができます。
こうした性質から、木造の建物は光熱費がかかりにくく、ランニングコストを節約できます。

減価償却が短くて節税になる
国税庁が定めた構造別の倉庫の減価償却できる年数は次の通りです。
木造・合成樹脂造のもの・・・15年
木骨モルタル造のもの・・・14年
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの・・・38年
れんが造・石造・ブロック造のもの・・・34年
金属造のもの(4mmを超えるもの)・・・31年
金属造のもの(3mmを超え、4mm以下のもの)・・・24年
金属造のもの(3mm以下のもの)・・・17年
木造は15年なのに対して、鉄骨造は長くて31年です。
つまり、建築コストが同じだった場合、木造の方が1年あたりの減価償却費が多くなり、節税しやすくなります。
木造は様々なコスト面のメリットがあると言えます。
倉庫を木造にするデメリット3つ
この章では倉庫を木造にするデメリットをご紹介します。
| 1 | 建物の品質が安定しない |
| 2 | 害虫対策をしなければいけない |
| 3 | 構造の自由度が低い |
建物の品質が安定しない
木材は育った環境や加工方法によって品質にバラツキがあります。
木造の倉庫を建てるとき、適切に部材を見極め、配置することが重要です。
つまり、建物の品質は職人の目や技術によって左右され、鉄骨造のような品質の安定性はありません。
害虫対策をしなければいけない
木材はシロアリの被害を受けやすいのが難点です。
シロアリに部材が食べられると、耐久性が落ちてしまいます。
また、シロアリによる被害はなかなか発見しづらいため、気づかないうちに被害が大きくなっているということもあります。
そこで、木造の倉庫では害虫対策が欠かせません。
構造の自由度が低い
木造は鉄骨造に比べてデザインの幅が狭いです。
特に、鉄骨造で作れるような大空間を実現することは難しいです。
そのため、大きくて広い空間を持つ倉庫にしたい場合や、できるだけ理想に合ったデザインにしたいという場合は鉄骨造が合っているでしょう。
最近は技術の進歩によって、木造でも広い空間を作ることができるようになっていますが、その際は普通の構造よりもコストがかかることがあるので注意が必要です。
倉庫を建てるなら鉄骨造と木造どっちがいい?
鉄骨造と木造、それぞれどんな方におすすめかをまとめました。
鉄骨造が向いているケース
- 耐久性や耐震性を重視したい
- 建物に安定した品質を求める
- 遮音性が欲しい
- 倉庫に大空間が欲しい
- 構造やデザインにこだわりたい
木造が向いているケース
- 建築コストを抑えたい
- どうしても建てたい土地がある
- 光熱費を削減したい
- 節税したい
- 工期をできるだけ短くしたい
まとめ
倉庫は7割強が鉄骨造、2割が木造と言われていて、鉄骨造で建てられるケースが圧倒的に多いです。
鉄骨造と木造はそれぞれメリットやデメリットが異なり、どちらを選ぶべきかは倉庫に対して何を求めるかによって異なります。
もしもどちらにするか迷った場合は建設会社に相談しましょう。